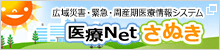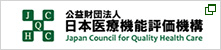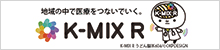Pickup News
- 2024.04.22
- 2024.03.31
- 2024.03.07
- 2024.02.14
- 2024.02.08
-
2024.02.08
能登中部保健医療福祉調整本部において、本部活動を行うDMATロジスティックチームが本部運営の引き継ぎ、病院・福祉施設の支援、在宅・支援者の支援等のため、2/8~2/14まで派遣
- 2024.01.23
- 2024.01.19
- 2023.12.25
- 2023.09.20
- 2023.07.05
- 2023.05.29
- 受付時間
-
午前:8時30分~11時午後:13時~16時
- 休診日
- 土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12月30日~1月3日)
- 面会時間
- 13時~16時
新着情報
- 全て
- 重要
- 一般
- 患者さんへ
- 採用情報
- 2024.04.22一般
- 鯉のぼりの展示
- 2024.04.01患者さんへ
- 4月の病児保育室の休室日を公開しました
- 2024.04.01患者さんへ
- 4月の診療予定表を公開しました
- 2024.03.31一般
- 整形外科の田巻達也先生の記事が四国新聞「医療最前線」に掲載されました
- 2024.03.07患者さんへ
- 通所リハビリテーションの送迎サービスを始めました
- 2023.04.07重要
- 面会制限緩和のお知らせ
- 2023.04.07重要
- 新型コロナウイルス感染症に関わる当院の対応について
- 2023.03.09重要
- マスク着用の考え方について
- 2022.10.14重要
- 新型コロナウイルス感染症に関わる当院の対応について
- 2022.09.22重要
- 選定療養費価格変更について(2022/10/1より)
- 2024.04.22一般
- 鯉のぼりの展示
- 2024.03.31一般
- 整形外科の田巻達也先生の記事が四国新聞「医療最前線」に掲載されました
- 2024.02.08一般
- 人工関節置換術支援ロボット「Makoシステム」導入に関する記者発表会が開催されました
- 2024.04.01患者さんへ
- 4月の病児保育室の休室日を公開しました
- 2024.04.01患者さんへ
- 4月の診療予定表を公開しました
- 2024.03.07患者さんへ
- 通所リハビリテーションの送迎サービスを始めました
- 2024.03.01患者さんへ
- 3月の病児保育室の休室日を公開しました
- 2024.03.01患者さんへ
- 3月の診療予定表を公開しました